社内SEとは?「楽」「やめとけ」と言われる理由は?役割や向いている人の特徴も解説

「社内SE 楽」「社内SE やめとけ」「社内SE きつい」といった言葉は、転職サイトや掲示板などネット上でよく見かける表現です。
たしかに、残業が少なく安定して社内で働けるというイメージから「働きやすい職種」として紹介されることも多く、キャリアにおいて人気の高い選択肢の一つとなっています。一方で、思っていたより業務範囲が広かったり、望んでいた業務ができなかったりと、イメージとのギャップに悩む声も少なくありません。
この背景には、社内SEの仕事内容や役割が、社内のIT環境や体制、外部ベンダーとの関係性などによって大きく異なるといった実情があります。
そこで今回は、そうした違いを踏まえながら、「社内SEの仕事内容や役割」について詳しく解説します。「楽」と言われる理由、逆に「きつい」と言われる理由、また向いている人の特徴も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
社内SEとは?役割や仕事内容
社内SEとは「社内システムエンジニア」の略で、基本的には対内的なシステムの開発などを行う職種・役割を指します。システムエンジニアというと、自社製品の開発や客先常駐・受託開発などのクライアントワークをイメージされがちなため、それらと区別するために“社内”SEと呼ばれます。
社内SEが担う業務は多岐にわたりますが、大きく分類すると以下のような領域に分けられます。実際にはこの中の一部のみを担当する場合もあれば、複数の領域を兼任するケースもあります。
- 社内システムの企画・開発
- 社内システムの運用・保守
- ヘルプデスク対応
- 情報セキュリティの管理
- 社内ネットワークの管理
社内システムの企画・開発
社内SEの業務といえば、やはり社内システムの企画や開発でしょう。現場の業務フローや困りごとを理解したうえで、「どのような仕組みを作れば社内の業務を効率化できるか」を検討し、最適なシステムをつくります。
自社でシステムを構築する・している場合、社内SEは企画から要求定義、開発、テストに至るまで全工程を主導することになります。自身の担当領域にもよりますが、サーバーの用意や開発環境の整備、仕様技術の選定、実際のプログラミングなど、広範な知識が必要です。
一方で、近年はクラウドサービスなどを中心に外部のプラットフォームに一部相乗りすることも増えました。たとえば AWS や Microsoft Azure などでサーバーを用意すれば、ある程度の作業を省略することができます。そのため、“社内システム”とはいっても、外部サービスの理解や使用経験も求められるようになっています。

社内システムの運用・保守
システムを安定して使い続けるためには運用・保守が必要ですが、それも社内SEの重要な業務のひとつです。日々の監視やトラブル対応、ソフトウェアのアップデートなどを行い、システムが正常に稼働し続けるよう支えます。
また、業務変更にともなう設計の見直しや、利用者からのフィードバックへの対応など、運用中の課題に向き合いながら、長く使われる仕組みを維持・調整していきます。
ヘルプデスク対応
社内SEといえば前述の社内システムの企画・開発や運用・保守というイメージが強いですが、会社によっては社員からのITに関する問い合わせ対応も業務に含まれます。システムとは関係ないPCの不具合やネットワークのトラブル、ITツールの使い方などの問い合わせに対応することもあります。
対応方法は口頭やチャット、メールによるやり取りが主流ですが、リモート操作や実際に現場に出向くこともあります。対応のスピードや丁寧さが求められるため、正確な知識はもちろん、社員との円滑なコミュニケーションも欠かせません。
情報セキュリティの管理
近年、情報漏えいやサイバー攻撃による被害が増加しており、企業におけるセキュリティ対策の重要性はますます高まっています。システムの管理などと併せて、社内SEがセキュリティ面の対応を担当している企業もあります。
具体的には、ウイルス対策ソフトの導入・更新やアクセス制御の設定、ID・パスワードの管理、不要なアカウントの削除などの業務が挙げられます。一般的には情報システム部門やセキュリティ部門が担う業務ですが、社内システムの開発や運用の延長として、社内SEが情報セキュリティの管理も任されてしまうケースも少なくありません。
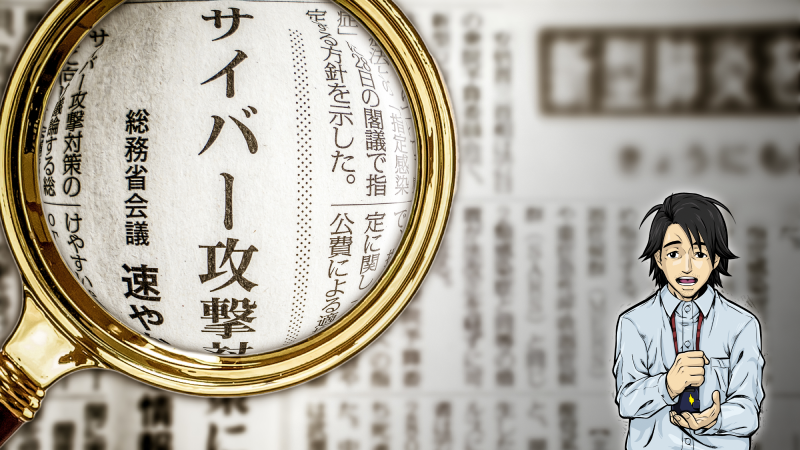
社内ネットワークの管理
社内SEがネットワークの管理を担っている企業もあるでしょう。たとえばインターネット回線の調達やルーターの設定、無線LAN環境の整備などです。こちらも一般的には情報システム部門が担う業務ですが、社内SEが情シス的な役割を求められることはよくあります。

【ちなみに】情シスとの違い
社内SEの仕事内容を理解すると、「それって情シスの仕事とどう違うの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
「情シス」とは「情報システム担当」「情報システム部」の略称で、企業のITインフラ全体を統括し、ネットワークやサーバーの構築・運用、セキュリティ対策、社内システムの管理、デバイス類の整備など、ITに関する幅広い業務を担当します。
一方、「社内SE」は元来その名の通り「社内のシステムを開発(エンジニアリング)する職種」でした。しかし、ITの進歩やパッケージシステム・クラウドサービスの普及により、一定クオリティの業務システムが簡単に手に入るようになったことで、社内システムを自社開発する企業は減少し、伴って社内SEはIT関連業務全般を担う役割へと変遷していきました。
社内SEが体系化された部門へと進化した姿が「情シス」であるという見方もあったり、差別化のために実際に開発(エンジニアリング)を行う技術職のみを社内SEと捉えたりと、両者の境界線は非常に曖昧です。
情シスと社内SEの具体的な役割は組織の規模やIT体制によって異なり、「その会社において何を求められているか」「どこまでの業務を担っているか」を正しく理解することが大切です。

組織体制によって異なる社内SEの役割
社内SEの役割は、組織体制によって大きく変わります。ここでは、所属する組織の属性が社内SEの役割にどう影響するかを見ていきます。
情報システム部門に所属する場合
情報システム部門がある企業では、社内SEはシステム開発・管理を担う技術職として位置づけられることが多いでしょう。となりにはネットワーク担当やセキュリティ担当、ヘルプデスク担当などがいたりと、専門性によって分業しているケースも少なくありません。一般的な社内SEのイメージに最も近いと言えるでしょう。
システム開発部門に所属する場合
システム開発部門に所属する場合、情報システム部門に所属するよりも更に社内システムの開発に寄った業務が中心になります。ネットワーク構築やセキュリティ対策、デバイス管理などの情シス的な業務は別部門が担っているケースが多いため、社内SEはプログラミングなどの技術的な業務を任されることがより増えるでしょう。
(前述の通り、自社製品のシステム開発部門とはここでは区別します。)
IT企画・DX推進部門に所属する場合
IT企画やDX推進などのIT関連部門に所属する社内SEは、システム運用にとどまらず、システム導入の企画や業務改善の提案など、上流工程に関わることが多くなる傾向があります。現場の業務フローを理解したうえで、ITを活用した業務改革の提案を行うなど、経営に近い視点が求められるでしょう。
どこにも属さない場合
「情報システム部」や「IT部」などの明確なIT関連部門がない企業では、経営直下や総務部などに社内SEが配置されることが多く、実質的に「IT関連のなんでも屋」になっていることがあります。このようなケースでは、PCの設定やITツールの管理、さらには「Wi-Fiの調子が悪い」といった日常的なトラブル対応まで幅広く求められることがあります。業務の線引きが曖昧になりやすいですが、社員とのコミュニケーションが活発なため、よりビジネスに寄ったキャリアを歩みやすいでしょう。この場合、社内SEではなく「IT担当」と呼称されることが多いかもしれません。
.png)
IT体制によって異なる社内SEの業務範囲
社内SEがどこまでの業務を担うのかは、企業のIT体制によっても変わります。特に、どこまでを社内で対応し、どこからを外部ベンダーに任せているかという切り分けは、社内SEの役割に大きな影響を与えます。
すべてのIT業務を社内で対応する企業では、社内SEはシステム開発や運用保守、トラブル対応まで幅広く関わります。エンジニアとしてのスキルを広く活かせる環境ですが、業務負荷も高くなりがちです。
開発を外部委託し、運用保守を社内で対応する体制では、社内SEは企画やベンダーとの調整、カットオーバー後の対応が中心となります。逆に、開発を社内で行い、運用保守を外部委託する体制では、社内SEはシステムの設計・開発に集中することになるでしょう。どちらにしても社外と連携して業務を行うことになるため、ビジネススキルを磨くことができますが、実務が運用に寄るか開発に寄るかで違いが出てきます。
さらに、IT関連をほとんどアウトソースしているような体制では、社内SEが社内とITベンダーをつなぐハブのような役割になることもしばしばです。この場合、適切なベンダーの選定や導入したいシステム・ツールの予算策定、IT戦略の立案など、ビジネスサイドに寄った業務が大半を占めることになります。これはこれで社内SEにおけるひとつのキャリアと言えるでしょう。
社内SEが「楽」と言われる理由
ここまで、社内SEの仕事内容が企業によっていかに多様であるかを見てきました。そんな中で、巷では「社内SEは楽」という声を聞くことがあります。実際の業務負荷は企業によって大きく異なりますが、「楽」と言われがちなのは以下のような状況に置かれた社内SEであると考えられます。
システムが安定運用フェーズにある場合
システムの本稼働がすでに完了し、初動を乗り越えて安定した状態に入ると、業務の大半は運用監視や改善対応になります。開発真っただ中に比べると落ち着いて見えるため「楽」という印象を持たれがちですが、「システムを安定して稼働させ続ける」というのもそれはそれで大変なお仕事です。
システムの運用保守をアウトソースしている場合
委託範囲にもよりますが、システムの運用保守をアウトソースしている場合、社内SEは日々のトラブル対応や定型作業から解放されます。緊急対応の頻度も比較的少なく、業務範囲が限定的に映ることから、「楽」に見られることがあります。とはいえ、運用保守をアウトソースするほどのシステムを自社で抱えているわけですから、仕様変更や改善対応といった業務の負荷が高い可能性も高いでしょう。
ヘルプデスク業務が中心の場合
社内SEと名乗っていても、実際の業務がヘルプデスク対応に偏っているケースもあります。この場合、システム開発のように納期に追われたり、予期せぬ仕様変更やトラブルで長時間の残業が発生するリスクが比較的低く、「楽」に見られがちです。一方で、IT化が進んでいる昨今の企業ではヘルプデスク業務にも広範な知識が必要とされ、かつそれを分かりやすく説明しなければならないため、環境によってはストレスが高くなる可能性もあります。
社内SEが「きつい」「やめとけ」と言われる理由
前述のように社内SEは「楽」と言われがちな一方、逆に「きつい」「やめとけ」という声を聞くこともあります。ここでは、社内SEが「きつい」「やめとけ」と言われる理由としてよく挙げられるポイントを紹介します。
意外と社内・社外ともにコミュニケーションが多い
社内SEは一見、社内向けの技術職というイメージが強い一方で、実際には社内外とのやり取りが多く発生することがあります。別部門からの要望やトラブル対応、外部ベンダーとの調整など、コミュニケーションが日常的に求められる場面も少なくありません。
また、社内の関係者が多岐にわたる場合、システムの導入や改修にあたって、方向性や要件についての合意形成に手間がかかることもあります。それぞれの部署に異なる事情や優先順位がある中で、バランスを取りながら調整を進めるのは容易ではなく、業務の中でも特に神経を使う場面のひとつといえます。
「止めてはいけないシステム」へのプレッシャー
社内SEが担当するシステムの中には、業務に欠かせない「止めてはいけないシステム」が含まれていることがあります。こうしたシステムは、たとえ社内向けであっても、24時間体制での稼働が求められる場合があり、障害発生時には深夜や休日でも対応が求められるケースも出てきます。常に「止めてはならない」というプレッシャーがあり、こうした環境に身を置いていると、「思っていたよりきつい」と感じる人も少なくありません。
キャリアを築きづらいと感じることもある
社内SEの業務は自社の業務システムに深く関わることが多いため、汎用的な技術スキルが身に付きにくいと感じることがあります。特定の環境に特化した経験は、他社に移った際にそのまま通用するとは限らず、将来的なキャリアの展望に不安を抱くケースも少なくありません。
特に、業務内容がヘルプデスク対応に偏っている場合、構築や設計といった技術経験を積む機会は限られてしまいます。一方で、ユーザー対応や業務部門との調整などを通じて、ビジネス寄りのスキルは得られるでしょう。どのような経験を積めるかは企業によって異なるため、自身のキャリアパスと照らし合わせて考えておくことが重要です。
社内SEに向いている人の特徴
それぞれの企業で求められるスキルや働き方に違いがあるとはいえ、社内SEに共通して向いているとされる人物像もあります。ここでは、社内SEに向いている人の特徴を4つのタイプに分けてご紹介します。
- 事業全体に関わりたい人
- マルチタスクに抵抗がない人
- 学習意欲が高い人
- 人をサポートするのが好きな人
事業全体に関わりたい人
システムは一部署だけで完結するものではないため、社内SEはキャリアを積めば積むほど複数の部門と連携しながらプロジェクトを進める機会が増えます。その結果、会社全体の業務構造や課題を俯瞰的に理解できるようになるでしょう。広い視野で仕事に取り組みたい人には意外と適している職種です。
マルチタスクに抵抗がない人
社内SEは同時に複数の案件やタスクを抱えやすい職種です。システムの運用保守や外部ベンダーとの調整に加え、ヘルプデスク的な業務も兼任している場合はさらに複数の業務を同時並行でこなすことも珍しくありません。ひとつの作業に集中するというよりは、優先順位をつけながら臨機応変に動くことが求められるため、マルチタスクに抵抗がない人には向いているでしょう。
学習意欲が高い人
社内SEはIT技術や業務の変化に対応するために、継続的な学習が不可欠です。IT技術は日々進化しており、新しいツールやシステムが次々と登場しています。それに合わせて自身のスキルをアップデートしていくことが必要になるでしょう。
また、社内SEは単にシステムを管理するだけでなく、社内の業務をより効率的にするための提案や改善を担うこともあります。こうした取り組みには、IT以外の業務知識や、社内の課題への深い理解も必要です。変化に前向きで、新しいことを吸収するのが苦にならない、学習意欲が高い人には特に向いていると言えます。
人をサポートするのが好きな人
社内SEの仕事は、社内の業務がスムーズに進むように支える「裏方」の役割が多くを占めます。たとえば、トラブルの対応や業務フローの改善、使いやすいシステム・ツールの提案など、技術を使って社員を助ける場面が日常的にあります。
表立った成果が見えにくいこともありますが、「人の役に立ちたい」「困っている人をサポートしたい」という気持ちを持っている人には、やりがいを感じやすい仕事です。縁の下の力持ちとして支えることに喜びを見出せる人に向いているでしょう。
社内SEは、企業のITを内側から支える重要な役割を担っており、その働き方や求められるスキルは企業の体制や方針によってさまざまです。
近年はDXの推進により、業務改善やシステム刷新を担う社内SEの存在がこれまで以上に重要になっています。単なる管理者ではなく、会社の変化を支えるキーパーソンとして期待される場面も増えてきました。
「楽」「きつい」といった評判にとらわれるのではなく、実際にどのような役割を担うのか、自社や志望先の体制を正しく理解することが大切です。

