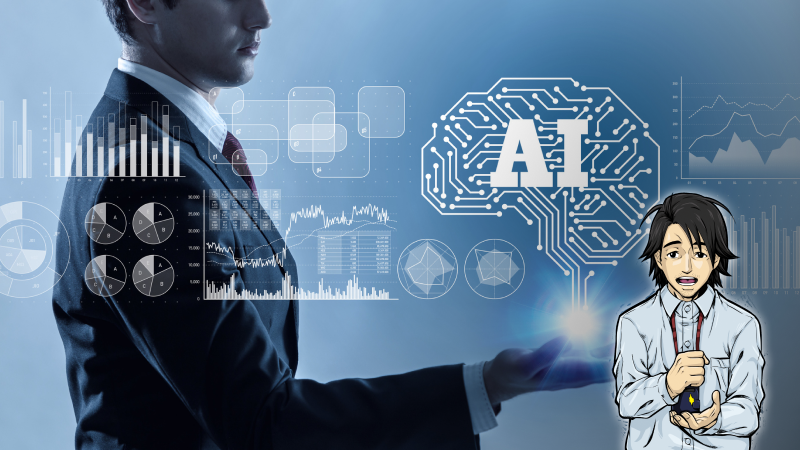生成AIの社内活用事例まとめ|導入メリットや注意点までわかりやすく解説
.png)
近年、ChatGPT をはじめとする生成AIの登場により、ビジネスにおけるAI活用が加速しています。しかし、「具体的にどう業務に活かせるのか?」という疑問を抱えている方も少なくありません。
そこで今回は、生成AIの社内活用事例をご紹介します。また、導入メリットや、導入時に考慮すべきリスクとその対策についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
〈この記事を読んでわかる内容〉
- 生成AIとは何か?
- 生成AI導入のメリット
- 生成AIの具体的な使われ方
- 生成AI導入時のリスクと対策
生成AIとは?
生成AIは、テキストや画像、音声、コードなど、多様なコンテンツを自動で創り出す人工知能技術です。この技術は、大量のデータから学習し、その中に潜むパターンや構造を理解することで、まったく新しいデータを生成します。従来のAIがデータ分析やパターン認識に長けていたのに対し、生成AIは「ゼロから何かを生み出す」能力を持っています。
生成AIには以下のような種類があります。
- テキスト生成AI:文章作成や要約、翻訳、アイデア出しなどに活用
- 画像生成AI:イラストやバナー、商品イメージなどのビジュアル生成に活用
- 音声生成AI:ナレーション音声、案内放送などの音声コンテンツに活用
- 動画生成AI:動画の自動編集、説明動画の生成などに活用
これらの技術が進化することで、ビジネスにおける活用の幅は飛躍的に広がっています。

生成AI導入のメリット・効果
生成AIは、文章作成やデータ分析、問い合わせ対応など多岐に渡る業務で活用されており、企業の生産性向上や新たな価値創造に大きく貢献しています。ここでは主なメリットを紹介します。
業務効率の向上
生成AIを活用することで、人間が時間を要する文章作成やレポート作成、情報整理といった作業を自動化し、迅速な処理が可能になります。これにより、社員は定型業務から解放され、より創造的な業務に注力できるようになります。
品質の均一化・標準化
人によるばらつきが出やすい文章や回答の質をAIが一定に保つことで、顧客対応の質が安定し、社内ドキュメントの品質も向上します。
新たな価値創造の支援
生成AIはアイデア出しや企画書の作成支援、データ分析結果の要約など、クリエイティブな業務にも力を発揮します。人間の思考を補完し、新しい発想やサービスの開発に役立ちます。
顧客満足度の向上
個々の顧客に合わせたパーソナライズされたサービス提供や、24時間365日の問い合わせ対応など、顧客との接点を強化することで、顧客満足度の向上に貢献します。
社内業務における生成AIの具体的な活用事例
ここでは、生成AIが多様な業務でどのように活用されているか、具体的な使われ方と実際の事例を以下の分野に分けてご紹介します。
- マーケティング・広報
- 営業・企画
- カスタマーサポート
- 開発・研究
- 人事・管理
- デザイン
マーケティング・広報業務での活用
マーケティングや広報分野は、生成AIの導入が特に進んでいる領域のひとつです。アイデア出しからコンテンツ作成、データ分析に至るまで、業務の質とスピードを両立させるツールとして注目を集めています。
たとえば、SNSの投稿文やキャンペーンコピーの下書きをAIが生成することで、担当者はアイデアの幅を広げつつスピーディに発信内容を組み立てることができます。また、社内資料やニュースリリースのたたき台をAIで作成し、最終調整だけを人間が担うといった使い方も広がっています。
さらに注目されているのが、市場調査やトレンド分析への活用です。AIを活用してデータ分析を行うことによって、消費者の声をリアルタイムで把握したり、市場の潜在的なニーズや競合の動向を迅速に洗い出したりすることが可能になります。これにより、データに基づいた戦略的な意思決定ができるようになります。
大手飲料メーカーでの事例
ある大手飲料メーカーでは、新商品のCM制作に生成AIを活用し、AIがCMのアイデアや出演者を提案することで、人間とAIが協力して斬新なクリエイティブを生み出すことに成功しました。
また、別のプロモーションでは、生成AIを用いて商品の擬人化キャラクターを制作しました。AIがキャラクターの見た目から声、セリフまでを生成し、SNSや YouTube での発信に活用することで、短期間で大量のコンテンツを生み出すことを可能にしています。
営業・企画業務での活用
営業や企画の業務では、提案書や資料作成、商談準備など、思考とアウトプットを高速で繰り返す作業が多く発生します。生成AIは、このような場面で業務の下支えとして活用が広がっています。
たとえば、新しい企画の構想段階で生成AIに簡単な指示を出して関連アイデアや構成案を出力させることで、担当者自身では思いつかない視点を得られることがあります。また、過去のデータやヒアリング内容をもとに、提案資料のたたき台やメール文面を自動で作成し、そこからブラッシュアップしていくことで作業時間を大幅に短縮できます。
営業現場では、生成AIの活用により、商談準備の効率が大幅に向上しています。顧客情報や業界動向の要約・整理を短時間で行えるため、準備時間の短縮が可能です。さらに、商談後の議事録作成や、次回の提案内容の要点整理にも生成AIを応用でき、多岐にわたる業務での活用が期待されます。
大手食品メーカーでの事例
ある大手食品メーカーでは、営業活動を支援するAIアシスタントを独自開発しました。このツールは、営業担当者が顧客情報などを入力すると、過去の成功事例や商品データ、市場トレンドなどをAIが分析し、最適な提案資料を瞬時に自動で生成します。
AIアシスタントの導入により、営業担当者は資料作成にかかる時間を大幅に短縮し、より多くの時間を顧客との商談や関係構築に充てられるようになりました。これにより、営業活動の効率が向上しただけでなく、顧客一人ひとりに合わせた質の高い提案が可能となり、成約率の向上にもつながっています。
カスタマーサポートでの活用
顧客サポートの現場では、日々膨大な量の問い合わせに対応する必要があり、迅速かつ正確な情報提供が求められます。生成AIは、こうした業務において、問い合わせ対応の効率化と品質向上に貢献しています。
具体的には、生成AIとチャットボットを組み合わせることで、問い合わせ内容に合わせた柔軟な回答が可能になり、従来のFAQでは対応が難しかった個別のニーズにも応えられます。さらに、対応履歴の要約や、問い合わせ内容に基づく自動レポート作成といった活用も進んでいます。
大手金融機関での事例
ある大手金融機関は、生成AIを活用した音声応対型のAIオペレーターサービスを導入しました。株価やNISA関連など幅広い問い合わせに即時対応できるこのサービスは、社内に蓄積された膨大な情報から最適な回答を瞬時に導き出し、高精度な応答を可能にしています。これにより、今後増加が予想される問い合わせにもスムーズに対応する体制を構築しました。
さらに、「一般的な問い合わせ」領域でも24時間対応を開始しました。顧客の利便性向上に加え、コンタクトセンターの混雑緩和にも貢献しています。
開発・研究分野での活用
生成AIは、開発・研究の現場でも活用が進んでいます。ソフトウェア開発においては、コードの自動生成やレビュー、ドキュメント作成の支援により、エンジニアの生産性を高める役割を果たしています。
また、研究分野では論文の要約や関連文献の検索支援、仮説立案の補助など、多岐にわたるタスクでAIが活躍しています。大量の情報から重要なポイントを抽出し、効率的に知見を深めることが可能になりました。
さらに、生成AIは複雑な数式やアルゴリズムの解説、シミュレーションの構築支援にも応用されており、研究者の専門的な作業負荷を軽減しつつ、新しい発想や発見を促進しています。
大手IT企業での事例
あるIT企業では、過去のソースコードや設計資料を学習させた社内ツールを使い、コードの自動生成や修正提案、レビューコメントの下書きなどをAIがサポートしています。これにより、エンジニアは繰り返しの作業から解放され、より高度な設計や創造的な改善業務に集中できるようになりました。
また、テスト工程でも、AIがテストコードやケースの自動作成を支援しています。この取り組みによって、ヒューマンエラーの防止や品質の安定にもつながり、開発スピードと成果物の品質を両立させる体制が構築されています。
人事・管理部門での活用
人事、総務、法務といった管理部門では、多岐にわたる文書作成や手続き業務が発生し、定型作業と判断業務が複雑に絡み合っています。これらの分野においても、生成AIを導入することで、業務効率の向上と品質の均一化が図られています。
たとえば、人事部門では求人票や社内通達文のドラフト作成に生成AIを活用することで、表現のばらつきを抑えつつ、スピーディに情報発信できる体制を整えることができます。
法務・総務部門では、契約文書の条文解釈やマニュアルの下書き、申請フォームの案内文など、正確さと説明力が求められる文書の草案作成に生成AIが活用されています。専門的な表現に不慣れな担当者でも、AIの提案をもとにベースを整え、確認・修正に専念できるため、全体の業務負荷を軽減できます。
製造業企業での事例
ある製造業企業では、自社開発のAIアシスタントサービスを活用し、全従業員が利用できる環境を構築しました。このツールは、勤怠管理や社内規定の問い合わせ対応、会議資料の要約、報告書のドラフト作成など、日常的な管理業務の負担を軽減しています。
特に、プロンプト添削機能や音声入力に対応しており、専門知識の有無にかかわらず、誰もが容易にAIを活用できる点が特徴です。また、社内公式情報を学習させることで、迅速かつ正確な回答が可能になりました。これにより、人事担当者や管理職は、より複雑で戦略的な業務に注力できる環境が整備されています。
教育・研修での活用
社員教育や研修の現場でも生成AIの活用が進んでいます。研修資料やeラーニングの教材作成において、生成AIは内容のドラフトや構成案をスピーディに作成できるため、担当者の負担軽減につながっています。
また、社員からの質問に対し、生成AIを活用したチャットボットが即時に回答する仕組みも導入されつつあります。これにより、講師や担当者への問い合わせ集中を抑え、受講者が自主的に疑問を解決できる環境を整えられます。
さらに、研修の振り返りやアンケートの要約もAIが行うことで、運営側は研修効果の分析や次回改善ポイントの抽出に注力できるようになります。こうしたサイクルは、教育の質を継続的に向上させることにもつながります。
グローバルテクノロジー企業での事例
あるグローバルテクノロジー企業では、AIを活用した教育プラットフォームを導入し、社員の学習と成長を支援しています。このプラットフォームは、AIが社員個人の役職、スキルレベル、学習履歴を分析し、最適な研修コンテンツや学習プランを自動で推奨することで、効率的かつ効果的な学習を実現します。
さらに、対話型AIを活用したキャリアコーチングツールも導入しており、社員はAIとの対話を通じて自身のキャリアパスを具体的に描き、成長に必要なスキルを明確にすることができます。これらの取り組みは、社員が目標を明確にし、自律的な学習を促進する環境を整備することに貢献しています。
デザイン分野での活用
デザイン分野でも生成AIは大きな変化をもたらしています。バナーやアイコン、資料のビジュアル素材などを短時間で自動生成できるため、従来よりも少ない工数で複数パターンのデザイン案を作成できます。特に広告代理店やインハウスデザイナーの現場では、手描きのラフやテキストの指示をもとに、AIが視覚的な草案を提案するケースが増えています。
また、ブランドガイドラインに沿ったAI画像生成のテンプレートを構築することで、社内の誰でも一貫性のあるデザインを作成できるようになり、業務の属人化を防ぐ効果もあります。単なる補助ツールとしてではなく、アイデアの起点やアウトプットの高速化ツールとして生成AIが機能することで、デザイン業務全体の生産性が向上しています。
教育・クリエイティブ事業を展開する企業での事例
ある教育・クリエイティブ事業を展開する企業では、画像生成AIを導入し、画像素材の選定や加工にかかる時間を大幅に短縮しました。従来は制作チームが素材選びに費やしていた時間を半分以下に抑えることで、より効率的に質の高いデザインを提供できるようになりました。
生成AI導入時に注意したいリスクと対策
生成AIは業務効率化や新しい価値創造に大きな可能性を秘めていますが、その一方で、導入や利用時にはいくつかのリスクや注意すべきポイントがあります。ここでは、生成AIを安全かつ効果的に活用するために知っておくべき主なリスクとその対策について解説します。
セキュリティ・プライバシーリスクの管理
生成AIに機密情報や個人情報を入力する際、情報漏えいのリスクを十分に認識しておく必要があります。
まず、入力されたデータが学習データとして再利用されるリスクです。企業の機密情報や個人情報がAIの学習モデルに取り込まれ、他者の出力に現れる可能性があります。顧客や従業員の個人情報だけでなく、製品開発や研究データなども同様に危険にさらされます。
次に、不正アクセスによる情報漏えいです。多くの生成AIはクラウド上で運用されており、セキュリティ対策が不十分な場合、悪意ある第三者によってデータベースに侵入され、重要な情報が流出する可能性があります。
これらのリスクを回避するために、以下の対策が考えられます。
- 機密情報を入力しない運用ルールの徹底
- 学習データとして再利用されない設定の確認
- 自社専用の生成AIの構築
- セキュリティ対策の実装と監視
機密情報を入力しない運用ルールの徹底
最も基本的な対策は、「機密情報・個人情報を生成AIに入力しない」というルールを社内で明確に定めることです。ルールを明文化し、従業員への周知・教育を徹底することが重要です。
学習データとして再利用されない設定の確認
近年の生成AIサービスでは、AIモデルへのデータ学習の有無を選択できる場合が増えています。企業が利用する際は、利用規約や設定項目を確認し、データが学習に利用されないように設定を見直すことが重要です。
自社専用の生成AIの構築
生成AIを自社の閉じたネットワーク内で構築・運用することで、社内機密情報を入力しても、その情報が外部ユーザーの回答に利用されることを防ぎ、データ流出のリスクを低減できます。

セキュリティ対策の実装と監視
生成AIを運用するクラウドサービスに対しては、暗号化やファイアウォール、多要素認証などの基本的なセキュリティ対策が講じられているか確認するとともに、脆弱性への対応状況も定期的にチェックする必要があります。

ハルシネーション(誤情報の生成)
ハルシネーションとは、生成AIが根拠のない情報や事実と異なる内容をあたかも正しいかのように生成してしまう現象を指します。
業務でAIを利用する際に、間違った情報を鵜呑みにしてしまうと、誤った意思決定につながりかねません。また、こうした誤情報を発信してしまうと、企業の信頼性を損なう原因にもなります。
このようなリスクを回避するため、以下の対策を講じることが重要です。
- AIの出力結果は必ず人間が確認し、重要な意思決定や公的文書への利用は慎重に行う
- AIが出力した情報を安易に信用せず、複数の信頼できる情報源と照合し、その真偽を確認する
生成AIは、社内業務の幅広い領域で活用が進んでおり、文章作成や資料の下書き、カスタマー対応、データ分析など、さまざまな業務で生産性向上に貢献しています。属人化の解消や、リソースの有効活用といった面でも大きな効果が期待されており、多くの企業が導入に踏み出しています。
一方で、セキュリティ上のリスクやハルシネーション(誤情報の生成)といった課題も存在し、効果的に活用するためには、明確なルール設計や教育体制の整備が欠かせません。
情シスマンを運営するUSEN ICT Solutionsは、法人のお客様向けに Microsoft Copilot や Google Gemini といった生成AIを提供しています。また、生成AIの導入を支援するため、クラウド環境の構築から多様なセキュリティサービスまで、幅広いサポートを提供しています。
生成AIの導入をご検討中の方は、ぜひ以下よりご相談ください。